ブランドの棄損・それは偶然の産物ではない
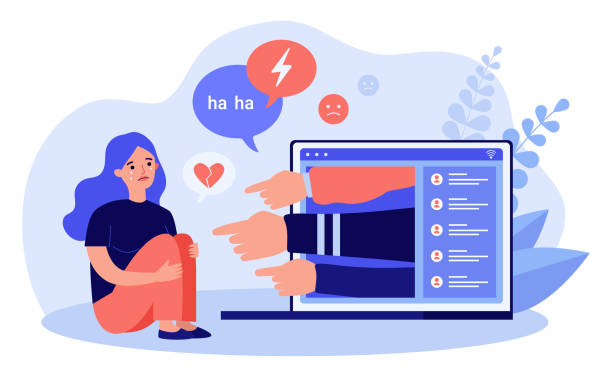
ごく最近では外食チェーンのアルバイトが非常識な言動をしたことで売上減少と株価暴落まで至りました。この件もかなりのブランドの棄損です。
ここでは、世界のブランド棄損の事例をご紹介し、それを防ぐための対策までお伝えしています。
ブランドの棄損事例
ブランドを棄損から保護することは、あらゆる場面でブランドを取り巻く環境をまもり、最良の形で演出する気配りである
優れたブランドは顧客とのタッチポイントのあらゆるシーンで配慮されており、逆を言えばブランドの棄損が起こるケースは必然的にそれがないということになる。
〜元スターバックスマーケティング副社長・ナイキ広告宣伝部長 スコットベドべリ〜
ドルチェ&ガッバーナ(イタリア):人種差別広告

出典:ドルチェ&ガッバーナ Instagram
【ブランドの棄損事例概要】
2018年、ドルチェ&ガッバーナ公式SNSで、「中国市場向けに中国人を描いた動画が人種差別」だとされて炎上。そこに描かれていたのはイタリアのピッツアを、両手に持った箸で食べようとする中国人女性でした。※動画出演女性は後で「大げさにしてしまった。中国を辱めた」と謝罪
そしてさらにステファノ・ガッバーナ氏が中国人を侮辱軽視した発言をしてさらに炎上。
【結果・影響】
- 中国での不買運動・中国ECサイトの多くが商品削除
- ファッションショーの中止
- モデルの契約辞退・解除
ブランドの棄損要因は、文化的な鈍感さ・経営陣の不適切な言動でした。
経営陣の発言は目を疑ってしまうほどで、ブランドの棄損は頭になかったと思われます。
United Airline(アメリカ):搭乗者の強制降機

【ブランドの棄損事例概要】
2017年、「フライトがオーバーブッキング(過剰予約)でCAなど従業員を登場することを優先したい」という理由で、アジア人の男性医師が飛行機を降りるように言われたものの、手術の予定があるためにどうしても搭乗しなければならないとして拒否。
この男性は引きづりおろされ血を流しながら怯える様子の動画が拡散される。このあと空港最高責任者が送った保身の社内メールでさらに大問題へ発展
【結果・影響】
- 株価の急落:時価総額でおよそ10億ドルが飛ぶ
- 巨額の和解金発生:被害を受けたアジア人男性医師に解決金を支払う
- SNSではユナイテッドをボイコットというハッシュタグがトレンド入り
- 深夜番組で笑いのネタにされる
ブランドの棄損要因は、暴力行為とSNSでの拡散でした。飛行機の搭乗は安全が尊重されるものの、真逆のことが起こっています。オーバーブッキングについてユナイテッドエアラインの誤った初動対応や最高責任者の不適切な社内メールがとどめを刺しました
ユナイテッドエアラインでは、運航規則を大幅に変更し、当然ながら降機の際のルールは見直しを余儀なくされています。
Face book(META・アメリカ):プライバシー侵害

【ブランドの棄損事例概要】
Face Bookの2017年に起きたブランドの棄損は、以下のようにプライバシー侵害でした。
- ケンブリッジ・アナリティカ事件:ユーザーの個人データを第三者企業と不正に共有
- 米国テック企業はフェイスブックユーザーのメールアドレスを入手できていた
- 検索エンジンで、本人不同意でフェイスブックユーザーのフォロワーリストを閲覧できるようにしていた
- 米国の某企業に、ユーザーのメッセージの閲覧を許可していた
【結果・影響】
- SNSでDeleteFacebookのハッシュタグキャンペーンャンペーンが広がる。
- 以下の時系列で欧米における判決と罰金
.png)
- 米国FTC:ケンブリッジ・アナリティカ事件、同意命令違反約7,250億円2019年7月
- EU(アイルランド):EU→米国へのデータ移転問題 (GDPR違反)約1,570億円2023年5月
- EU(アイルランド):Instagramの児童プライバシー問題 (GDPR違反)約520億円2022年9月
- 英国ICOケンブリッジ・アナリティカ事件関連約7,000万円2018年10月
棄損要因は、FACEBOOKのサービスの基盤中の基盤である個人データの不適切な管理やデータ管理の不透明さでした。FACEBOOK社はこれに限らずブランド棄損の事例は少なくありません。
雪印乳業:異物混入(日本)

日本の食品業界における「安全神話」崩壊の象徴的な事例となってしまいました。
【ブランディング棄損の事例概要】
2000年、大阪府の雪印工場で生産された低脂肪乳を飲んだ約1万4,000人が食中毒症状になる。停電によって生産製造を停止した後、原料乳を常温で放置、細菌が繁殖した。さらに隠蔽工作があった。
【結果や影響】
- 消費者からの信頼は完全に失墜。
- 社名変更(雪印メグミルク)
- ※現在も当時のブランドの棄損のダメージはゼロではない。
棄損要因は品質管理の致命的な誤りと、危機管理の欠陥・情報開示の不備でした。
ブランディングの棄損を防ぐには何をすべきなのか?
上の事例はどれも企業側からすれば初速は日常的なほんのささいなミスや失態に過ぎなかったかもしれません。
SNSがなかった時代は情報が拡散されるスピードは遅かったですし、ニュースで取り上げられないことも多々あったでしょう。
冒頭でご紹介した最強のブランディングやマーケターと呼ばれるスコットベドべリ氏は以下のようにも言っています。
偉大なブランドを構築するには長い年月を必要とします。育成・守り、そして絶えず変わらない価値を注ぎ込んで誰からも愛される存在になるように願うことも大切。大切に育てればいつの日か誇れるブランドに育ちます。
「これでは対策と呼べない」と思われるでしょうが、上の事例に共通しているのはすべて「不適切な倫理観」であると言って間違いないように思います。
間違いや失敗の一つや二つは誰しもあるものですが、以下がブランド棄損の回避策になるでしょう。
- 顧客・ユーザーにとって企業は何を求められているのか?を深堀し、求められている価値観を日々創造・実戦する
- 危機管理マニュアルの整備:初動対応を明確化し、全従業員で共有
- SNSモニタリング体制の構築:炎上の早期発見と迅速な対応のための体制整備
- 従業員教育の徹底:関わる人員すべてにブランド理念の浸透と研修の実施
- 多様性と包括性の尊重:異文化理解を深め、差別的要素がないかのチェック体制を構築
日本の外食産業の失態が瞬く間にSNSで拡散されたように、現在はブランドの棄損も早いですし、長年にわたってWEB上に残り続ける性質(デジタルタトウ‐)もあります。
ここで必要なのは企業の従業員一人一人の倫理観や、企業人としての誇り以外の何ものでもないのだろうと思います。
以下はスターバックスのCEOハワードシュルツがCSRの代表が集まった世界大会で述べたスピーチです。
適切な言動をなす企業の姿勢が今ほど問われている時代はない。持続可能なビジネスを築くには良心とハートを持つことが必須です。
企業として適切なことをするのは、マスコミ向けではなく、それが自分の姿を映し出すものだからです。
上のスピーチは御尤もなことで、実戦し続けられる企業は極稀な存在であることも示唆しています。
御社のブランドを守るために、今日からできることは何かを以下でお問い合わせください。
弊社では香りによるブランディングを行っています。関連記事も御参考ください。


